「浄化槽の設置費用はどのくらい?」
「修理や交換費用が高くて困ってる」
浄化槽について上記のような悩みを持っている人もいることでしょう。
新築戸建てを建てるときに、地域によっては浄化槽の設置が必要です。
この記事では、浄化槽の設置や修理費用を徹底解説。浄化槽に関する費用を細かく紹介します。
特に浄化槽の修理費用は要チェックです。
自然災害による損傷であれば、火災保険が適用できる可能性があります。
新築一戸建てなら浄化槽にかかる費用は80万円~

環境庁が定める標準タイプの浄水槽の新規設置または交換にかかる費用例を、以下の表にまとめたので、ご覧ください。
| サイズ | 費用例 | 住宅の分類 |
| 5人槽 | 837,000円 | 130㎡(約40坪)以下 |
| 7人槽 | 104,3000円 | 130㎡(約40坪)以上 |
| 10人槽 | 1,375,000円 | 2世帯住宅 |
浄水槽は、住宅の分類によってサイズが規定されています。
一戸建ては5人槽の浄化槽が一般的です。
浄化槽の本体価格や工事費用を合わせると、80万円前後が相場です。
浄水槽の新規設置と交換にかかる費用は、ほとんど変わりありません。
ただし、トイレやキッチンなど水回りを改修する場合は別途工事費がかかります。
環境庁によると、浄水槽本体の耐用年数は30年です。
浄化槽の交換にかかる期間は3日~1週間程度です。
工事中は水が使用できない時間帯があるので、事前に確認しましょう。
浄化槽の年間維持費は5つの内訳で決まる

浄化槽の年間維持費は6万円〜です。
環境庁が設定している、浄化槽の年間維持費の標準値は以下の通りです。
| 5人槽 | 7人槽 | 10人槽 | |
| 保守点検費 | 21,000円 | 22,000円 | 23,000円 |
| 清掃費 | 26,000円 | 35,000円 | 50,000円 |
| 法定検査費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| その他 | 13,000円 | 19,000円 | 25,000円 |
| 合計 | 65,000円 | 81,000円 | 103,000円 |
ここでは、浄化槽の維持管理にかかる以下5つの費用について、詳しく解説します。
- 保守点検費:2万円~
- 清掃費:2万6,000円~
- 法定検査費:5,000円~
- ブロアの電気代:7,000円~
- 故障した場合の修理費用:7万円~
上記は浄化槽を適切に管理するために必要な費用なので、正しく把握しましょう。
①保守点検費:2万円~
浄化槽の保守点検にかかる費用は、年間2万円〜です。
保守点検は浄化槽の処理機能が低下していないかを検査し、浄化槽の周辺機器を調整するために行います。
保守点検の回数は年に3~4回が目安です。
ただし、浄化槽の種類や処理方式によって実施期間が異なります。
以下、浄化槽の種類別に見る保守点検の実施期間です。
| 浄化槽の種類 | 処理方式 | 年間実施期間(処理対象人員20名以下の場合) |
| 単独処理浄化槽 | 全ばっ気式 | 3月 |
| 単独処理浄化槽 | 分離接触ばつ気方式、分離ばつ気方式又は単純ばつ気方式 | 4月 |
| 合併処理浄化槽 | 分離接触ばつ気方式、嫌気ろ床接触ばつ気方式又は脱窒ろ床接触ばつ気方式 | 4月 |
自治体から委託を受けている業者に依頼すると、点検時期に業者から保守点検の通知が届きます。
②清掃費:2万6,000円~
浄化槽の清掃費は2万6,000円〜です。
浄化槽は使用するうちに、泥などの汚れが蓄積します。
汚れは浄化機能の低下につながるため、定期的にバキュームカーによる吸い出しや、周辺機器の洗浄が必要です。
浄化槽の清掃が必要な頻度は年1回で、清掃時期に委託業者から通知が届きます。
ただし、全ばっ気方式の浄化槽は、半年に1回以上の清掃が必要です。
清掃費用は委託業者によって異なります。
自治体によっては、浄化槽の清掃に対して2~3万円の補助が出ます。
③法定検査費:5,000円~
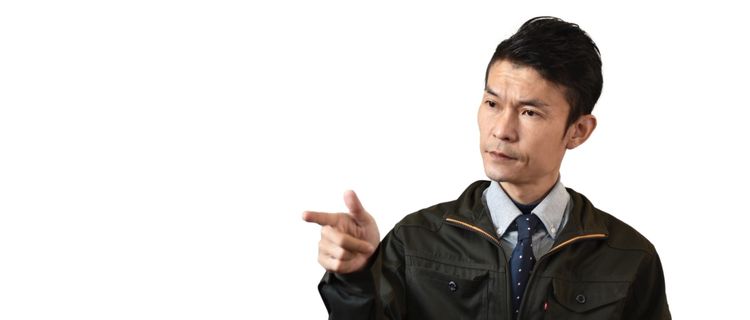
浄化槽の法定検査にかかる費用は5,000円〜です。
法定検査は、浄化槽の保守点検や清掃が定期的に実施されているか調べるために行われます。
法定検査が行われる時期は、以下の通りです。
| 検査の名称 | 時期 |
| 設置後等の水質検査 | 浄化槽を使い始めて3カ月~5カ月以内 |
| 定期検査 | 毎年1回 |
法定検査は知事が指定する業者が、以下3つの項目ごとに浄化槽が正常に働いているか確認します。
| 項目 | 内容 |
| 外観検査 | 水の流れの確認、悪臭・虫が発生していないかなど |
| 水質検査 | BODなどの水質測定 |
| 書類検査 | 保守点検と清掃の確認 |
法定検査の時期になると、保守点検を依頼した業者から通知が届きます。
④ブロアの電気代:7,000円~
浄化槽のブロアの電気代は年間7,000円~です。
ブロアとは、浄化槽内にいる水を浄化する働きをする微生物に、酸素を送り込むためのポンプです。
ブロアは日中の外出時や夜間も動かさなければならず、電気代の高騰で家計の負担になる可能性があります。
そこで、ブロアの電気代を節約する方法は、以下2つです。
- 消費電力の低いブロアに交換する
- タイマーで間欠運転に切り替える
ただし、上記の措置を行っても、法定検査で基準値を下回らないように確認が必要です。
⑤故障した場合の修理費用:7万円~
浄化槽が故障したときの修理費用の相場は、工事費込みで7〜12万円を見積もりましょう。
浄化槽本体の耐久年数は30年ほどですが、周辺機器の耐久年数は15年ほど。
台風や洪水などの自然災害で故障するケースもあります。
特に浄化槽を動かす「ブロア」の部分は故障しやすく、悪臭や異音の原因になります。
ブロアはホームセンターで2万円程度で手に入り、自分でも交換が可能です。
浄化槽の撤去費用は6万円~

浄化槽の撤去には、6万円ほどかかります。
浄化槽の種類や撤去方法によって費用が変動するため、撤去の際には以下をチェックしましょう。
- 撤去方法により金額が上下する
- 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換費用は約90万円
それぞれ詳しく解説します。
浄化槽の撤去方法と費用を比較
浄化槽の撤去方法には、以下の3種類があります。
| 撤去方法 | 施行内容 |
| 全撤去 | 汚水や浄化槽の本体、周辺機材を全て撤去 |
| 埋め戻し | 汚水と浄化槽の一部を撤去 |
| 埋め殺し | 汚水のみを撤去し、浄化槽本体は地中に残す |
撤去費用としては全撤去が最も高額で、埋め殺しが最も安いです。
ただし、埋め戻しや埋め殺しは不法投棄に該当するリスクがあるため、全撤去が推奨されています。
また、埋め戻しや埋め殺しを行った土地は資産価値が下落する恐れがあります。
新しい家を建てるときに地中に残った浄化槽の撤去を行う必要があり、追加工事費が発生するためです。
浄化槽を交換する時の費用の目安
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への交換費用は、90万円〜です。
環境庁が提示した交換費用の一例を見てみましょう。
【単独処理槽の撤去費用例(5人槽)】
| 内訳 | 費用例 |
| 清掃 | 29,900円 |
| 撤去工事 | 24,000円 |
| 処分 | 39,400円 |
| 合計 | 93,300円 |
【新しい浄化槽の設置費用例】
| 人槽規模 | 価格 |
| 5人槽 | 80.4万円 |
| 7人槽 | 98.4万円 |
| 10人槽 | 130.5万円 |
工期は3日~1週間程度です。
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への交換は国で推奨されている事業なので、自治体の補助金が利用できる可能性があります。
賃貸一戸建の浄化槽の維持管理費用は借主負担

賃貸一戸建ての場合、浄化槽の維持管理費用は基本的に居住者である借主が負担します。
定期的なメンテナンスにかかる費用は、上記で紹介したように6万円からです。
ただし、契約書の内容によっては貸主が負担するケースもあります。
経年劣化で浄化槽が故障した場合、修理費用は貸主の負担であることが多いでしょう。
賃貸アパートでは、浄化槽を含む基本設備の維持管理は貸主の責任です。
維持管理費用は家賃や共益費として、借主へ上乗せ請求されます。
浄化槽の設置に利用できる3つの助成制度

浄化槽の設置費用を安くするには、助成制度を活用しましょう。浄化槽の助成制度には、以下3つがあります。
- 自治体からの新築補助金
- 自治体からの転換補助金
- 市営浄化槽
浄化槽の新規設置や交換工事を検討している人は要チェックです。
①自治体からの新築補助金
新築を対象とした浄化槽設置費用の助成制度です。
新築補助金は自治体が独自に設けており、利用できないことも多いので、事前に確認しましょう。
以下は新築補助金が出る、岡山市の支給例です。
| 人槽規模 | 補助金額 |
| 5人槽 | 332,000円 |
| 6~7人槽 | 414,000円 |
| 8~10人槽 | 548,000円 |
補助金額や補助金の受け取り条件は、自治体により異なります。
居住エリアが下水道整備地区にある場合は、新築補助金は受けられないことがあります。
また、新築でも建売物件や増築による浄化槽の設置は、対象外とされることがあるので注意しましょう。
さらに、自治体の助成金は予算に達してしまうと募集終了日を待たずに受付を締め切ることが通常です。
「まだ大丈夫」と思うのではなく、利用したいと思ったらスピーディーに申し込むことが大切です。
②自治体からの転換補助金
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する際は、自治体の転換補助金が利用可能です。
転換補助金は国庫助成制度を利用しているため、新築補助金よりも多くの自治体で利用できるでしょう。
国庫助成制度とは、自治体が主体となって行う事業に対して、国が費用の一部を助成する制度です。
国庫助成制度を利用した助成制度では、浄化槽設置費用の4割を国や自治体が負担(自治体によって上限あり)します。
補助金の申請手順は、以下6ステップです。
- 自治体に浄化槽設置の申請をする
- 補助金交付申請書を提出する
- 自治体から補助金交付確定の通知が来る
- 浄化槽設置工事を開始する
- 工事が完了したら自治体へ請求書を提出する
- 補助金の交付を受ける
自治体によっては、上記の助成金制度以外にも補助金が申請できるので、窓口に問い合わせましょう。
③市営浄化槽

市営浄化槽は、個人宅に自治体が浄化槽を設置・管理してくれる制度です。
市営浄化槽の対象エリア内に住居がある場合、補助金制度は利用できません。
市営浄化槽では、設置費用の9割を国や自治体が負担します。
残りの1割は「分担金」として申請者が支払います。
市営浄化槽の設置後は、申請者は使用料として以下3つの料金を市町村へ毎月支払う必要があります。
- 水道代
- 電気料金
- 維持管理費用
市営浄化槽の維持管理は自治体が行うため、申請者が独自に業者と委託契約する必要はありません。
浄化槽の代表的な種類は2つ

浄化槽には、以下の2種類があります。
- 合併処理浄化槽
- 単独処理浄化槽(汲み取り式)
浄化槽は微生物の働きで水をきれいにする設備ですが、上記2つは機能が大きく異なります。
それぞれのメリットとデメリットとともに、特徴を見ていきましょう。
①合併処理浄化槽
合併処理浄化槽とは、トイレで流されるし尿や、台所や風呂などの生活排水をまとめてきれいにする浄化槽です。
下水道が整備されていない地域では、各住宅の地下に設置しなければなりません。
メリットとデメリットは、以下の通りです。
| メリット | 生活排水の汚れを90%除去できる
下水道処理場なみの機能がある |
| デメリット | 住宅敷地内に設置スペースが必要
処理能力に限界がある |
合併処理浄化槽は、水の汚れの90%を除去し、川へと排出します。
平成13年4月1日の浄化槽法改正により、現在「浄化槽」として認められているのは合併浄化槽のみです。
令和2年には、全国で10万基を超える合併浄化槽が新規設置されました。
②個別または単独処理浄化槽(汲み取り式)
単独処理浄化槽はトイレの汚物を処理するための浄化槽です。
台所や風呂から出た排水は浄化せず、そのまま川に流します。
平成13年の浄化槽法改正により、現在単独処理浄化槽の新規設置はできません。
現在設置されているものは、合併処理浄化槽への交換が進められています。
以下、個別浄化槽のメリット・デメリットです。
| メリット | トイレを水洗化できる |
| デメリット | 排水の浄化能力が低い
古くなった浄化槽が環境破壊などトラブルを起こしている |
単独浄化槽と混同されることのある汲み取り式とは、いわゆる「ぼっとん便所」です。
タンクにし尿を貯めて定期的にバキュームカーで処理する仕組みで、厳密には浄化槽ではありません。
合併処理浄化槽の2つの処理方法

家庭で使用される小型の合併処理浄化槽には、下記2種類の処理方法があります。
- BOD除去型(嫌気ろ床接触ばっ気方式)
- 高度処理型(脱窒ろ床接触ばっ気方式)
浄化槽は、国土交通大臣から認定を受けた工場で作られたものを使用しなければなりません。
以下でそれぞれの特徴を解説するので、浄化槽選びの参考にしてください。
①BOD除去型(嫌気ろ床接触ばっ気方式)
BOD除去型とは、微生物の働きで汚水を除去する浄化槽です。
BOD除去型の合併処理浄化槽は、以下4つの槽に汚水を通すことで水をきれいにします。
| 槽の名称 | 働き |
| 嫌気ろ床槽 | 水の汚れを固形物と液体に分解する |
| 接触ばっ気槽 | 微生物の働きで水の汚れを浄化する |
| 沈殿槽 | 水に残った汚れを分離し接触ばっ気槽に送り返す。
きれいになった水は次の槽に送る |
| 消毒槽 | 塩素剤で水を滅菌消毒し、河川に流す |
BOD除去型は、最もメジャーな小型合併処理浄化槽の処理方法です。
BOD除去率は90%以上で、下水道と同程度の処理能力を持ちます。
②高度処理型(脱窒ろ床接触ばっ気方式)
高度処理型は、BODに加えて水中に含まれる窒素の除去が可能です。
嫌気ろ床槽の代わりに脱窒ろ床槽があり、水の汚れを分離・浄化するのと同時に窒素を除去します。
接触ばっ気槽以下の働きはBOD処理型と同じです。
高度処理型は湾岸やダム集水域など、プランクトンが発生しやすい地域で導入されます。
窒素やリンが多い海域では、プランクトンが異常繁殖して赤潮が発生するため、BOD除去型では不十分です。
全国にある合併処理浄化槽のうち、30%近い割合で高度処理型が導入されています。
浄化槽を長く使うための3つのポイント

浄化槽を長く利用するために、以下3つの点に注意しましょう。
- 油や紙を浄化槽に流さない
- 食器用洗剤やカビ取り剤は適量を使う
- 浄化槽のマンホール上に重いものを置くときは注意が必要
普段の生活で意識的に取り組むと、浄化槽が長持ちします。
浄化槽の交換には多額の費用がかかるため、大切に使いましょう。
①油や紙を浄化槽に流さない
食用油や紙は、浄化槽に流さないよう気を付けましょう。
生活排水は浄化槽内部を循環して処理されますが、油や固形物は水に溶けづらく、浄化槽内部に留まり排水処理に支障を来たします。
また、浄化槽周りのパイプ詰まりの原因になるので、食用油や固形物をそのまま流すのは危険です。
食用油や固形物を捨てる際には、燃えるゴミとして処理しましょう。
油類は新聞紙やキッチンペーパーなどに染み込ませて捨てるのがおすすめです。
浄化槽の機能を低下させないように、浄化槽の使い方に気をつけましょう。
②食器用洗剤やカビ取り剤は適量を使う
食器用洗剤やカビ取り剤は適量を使いましょう。
市販されている通常の洗剤なら、除菌効果があっても浄化槽内の微生物に影響はありません。
ただし、塩素系漂白剤は大量に使うと微生物の働きを弱めたり、死滅させたりする可能性があります。
浄化槽を長持ちさせるなら、中性洗剤や「浄化槽対応」の表示がある洗剤を選びましょう。
また、トイレや風呂の汚れがひどい部分は、アルコールを吹きつけて汚れを拭き取る方法がおすすめです。
③浄化槽のマンホール上に重いものを置くときは注意が必要

浄化槽のマンホール上には、重いものを置かないようにしましょう。
浄化槽が埋められているスペースを駐車場にする場合は、施工業者にあらかじめ相談が必要です。
浄化槽が自動車の重みに耐えられるよう補強工事を行えば、普通車なら駐車しても問題ありません。
ただし、マンホールにタイヤが載ってしまうと、マンホールの蓋が壊れたり陥没したりする危険があります。
また、物置や倉庫などの移動できない構造物を、浄化槽のマンホールにかかるように設置することは禁止されています。
マンホールの蓋が開閉できず、清掃や保守点検の妨げになるためです。
浄化槽か下水道エリアかを決める5つの基準

新築を建てるときは、下水道か浄化槽エリアどちらにするかという観点でも検討しましょう。
具体的に考慮すべき点は、以下の5つです。
- 初期費用は浄化槽の方が安い場合がある
- 使用料は下水道の方が安い場合がある
- 災害多い地域なら浄化槽がおすすめ
- 下水道整備計画の有無を確認しておく
- 悪臭リスクを避けたいなら下水道がおすすめ
下水道が通っている地域に家を建てる場合は、無条件で下水道になります。
そのため、下水道か浄化槽かを自分で選ぶことはできません。
以下で詳細を見ていきましょう。
①初期費用は浄化槽の方が安い場合がある
浄化槽の設置工事の方が、下水道の引き込み工事より安く済む場合があります。
下水道の引き込み工事価格は、新築と「公共ます」の距離で決まります。
以下、各工事費の概要です。
| 工事内容 | 工事費 |
| 下水道引込工事(近くに公共ますあり) | 25~50万円 |
| 下水道引込工事(公共ますなし) | 50~100万円 |
| 浄化槽設置工事 | 80万円~ |
公共ますとは、台所やトイレなど家庭から出た汚水を1カ所に集めて、下水道本管に流すための容器です。
公共ますが道路の反対側など遠い場合は、100万円近い工事費用がかかることがあります。
②使用料は下水道の方が安い場合がある
1人暮らしをしている場合、浄化槽を設置するよりも下水道の方がお得なケースがあります。
浄化槽は保守点検など維持管理費がかかりますが、下水道は終末処理場で汚水を浄化するため、維持費は不要です。
ただし、下水道は使用料を支払わなければなりません。
下水道使用料は水道料金と連動しています。水をたくさん使うファミリー世帯ほど、浄化槽のメリットを感じやすいでしょう。
地域によっては、下水道環境が整備されていないエリアもあります。
浄化槽を設置したあとに下水道が整備されると、浄化槽の撤去と下水道引き込み工事が必要です。
下水道の整備計画は、各自治体のHPやパンフレットで公開されているため事前に確認しましょう。
③災害多い地域なら浄化槽がおすすめ

地震などの災害に強いのは浄化槽です。
被新潟中越地震の調査によると、ほとんどの浄化槽が通常通りに使用できたことがわかっています。
浄化槽は各家庭ごとに設置されているため、被災しても1週間〜10日程度で復旧可能です。
下水道は下水管と処理施設が一本につながった大掛かりなシステムなので、復旧に半年ほどかかるケースがあります。
また、浄化槽は構造的に地震に強く設計されています。
本体に使われる素材は、頑丈な強化プラスチックです。
ブロア以外の周辺機器が少ないシンプルな造りなので、地震による地盤変化に耐えられます。
④下水道の方が汚水の処理能力は高い
新築一戸建てで浄化槽の設置を検討している場合には、下水道整備計画の有無を確認しましょう。
地域内で下水道の整備がされた場合には、法律で1年以内に下水道への切り替え工事が必要です。
新たなに浄化槽を設置しても、無駄な費用になってしまいます。新築を予定している人は自治体窓口に問い合わせて確認しましょう。
⑤悪臭リスクを避けたいなら下水道がおすすめ
合併処理浄化槽と下水道はどちらも汚水の処理能力は高いですが、汚水を元の水質まで戻せるのは下水道です。
汚水の処理能力は以下の通りです。
| 汚水処理方法 | BOD除去率 |
| 下水道 | 99% |
| 合併処理浄化槽 | 90% |
| 単独処理浄化槽 | 60% |
BOD除去率で比較すると、下水道が最も優れていることがわかるでしょう。
また、浄化槽は水質の悪化や部品の故障により悪臭が発生するケースがあります。
下水道は最終処理場で汚水を管理・処理するため、臭いはほとんど発生しません。
浄化槽の費用に関するFAQ

基本的には、本体が完成する前でも後でも問題ありません。心配であれば、施工業者に確認しましょう。
水道料金に「下水道使用料」が含まれているかでわかります。明細書に左記料金が含まれている場合は、浄化槽は使われていません。
まとめ:浄化槽にかかる年間維持費を把握しておこう

浄化槽の設置には、本体価格を含めて80万円以上かかります。
さらに、法律で義務付けられた維持にかかる費用も発生します。
この記事を見返しながら、浄化槽の設置や維持にどのような費用がかかるかを把握しましょう。
浄化槽が壊れたら、修理が必要です。
当然、修理をするには費用がかかるため、浄化槽が壊れないような使い方を心掛けましょう。
浄化槽の設置を検討するさいは、費用無料で完全成果報酬型の火災保険申請サポートを選ぶとよいでしょう。
火災保険の申請は複雑な専門知識が必要なため、ご自身で給付金請求を行うと、不払い認定されたり、見落としや間違いが発生する可能性があります。
家全体の破損箇所の調査見積もりから、書類作成のアドバイスまでトータルで手厚くサポートします。
費用については完全成功報酬型のため、申請しても万が一給付金が得られなければ、一切費用がかからないのでリスクなく依頼できます。
「修復ナビ」ではご相談から火災保険の申請サポートまですべて無料で対応しています。また弁護士監修で、現地調査も一級建築士などのプロが行うため安心してご利用できます。
気になることがございましたら、まずはお気軽にメールやLINEでご相談ください。すべて無料で対応させていただきます。






コメント